『職場の教養』という冊子があります。
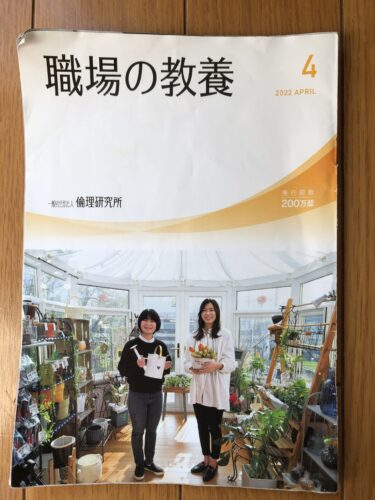
私、クローバーにとってお気に入りの冊子です!
なぜなら、冊子の内容には
- 心に残る内容
- ハッと気づきを与える内容
- 偉人の知恵等
が文章として描かれているからです。
『職場の教養』は、毎月、
一般社団法人 倫理研究所より発行されています。
『職場の教養』は、倫理研究所の法人会員になっているお店に行くと置いてあります。
数に限りはありますが、無料で頂けます!(*^▽^*)
毎日1話ずつ記されていて
- その日のテーマ
- 本文
- 今日の心がけ
が記されています。
今回は『職場の教養』2022年4月号から
- 4月7日
- 4月19日
- 4月30日
の心に残った3つの記事を紹介したいと思います。
4/7 世界保健デー
4/7のテーマは「世界保健デー」となっていました。
本文の中で特に心に残った内容を引用します。
今日は「世界保健デー」です。WHO(世界保健機関)憲章が設定された四月七日を記念して定められました。 (中略)
江戸時代の儒学者・貝原益軒が健康法を説いた『養生訓』には、「飲食、運動、睡眠」など現代でも参考になるような内容と共に、「怒りと欲を抑え、憂いと思いを少なくし、心を苦しめず」と心の持ち方が大切であると書かれています。
引用元:『職場の教養 2022年 4月号 10頁
という内容でした。
これを読んだ時
『江戸時代には健康法が確立していたんだなぁ~』
とビックリしてしまいました。
しかも、基本の「飲食、運動、睡眠」だけでなく、心のコントロールの仕方まで丁寧に記されていました。
「怒りと欲を抑え、憂いと思いを少なくし、心を苦しめず」の部分では、私、クローバーの場合、『憂い』が時々あり、それが自分の心を苦しめているな~と感じました。
何かあると、心が落ち込んでしまうコトがあります。(>_<)
まだまだでございます。
『憂いと思いを少なくし、心を苦しめず、心に優しく、自分に優しくしていきたい!』と思いました。
憂い
- 自分が思うようにならないで、つらい。苦しい。
- わずらわしい。気が進まない。
- つれない。つめたい。
- 悩ましい。せつない。心苦しい
出典元:コトバンク
WHOや貝原益軒さんが気になったので調べてみました。
WHO
厚生労働省のホームページには、『日本とWHO』について紹介されていました。
WHO・・・World Health Organizationの略です。
設立目的・・・「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」
設立日・・・1948年4月7日
加盟国・・・194カ国(2022年10月現在)
日本の加盟・・・1951年5月
2022年の世界保健デーのテーマ・・・「私たちの地球、私たちの健康」
「健康で幸福な生活」 = 「地球の健康」
「健康の危機」 = 「気候の危機」
私たちが「健康で幸福な生活」を送れるのは、「地球の健康」があってこそです。
「地球の健康」を維持するためには「気候の危機」から、いかに地球を守れるかです。
「気候の危機」が訪れると、災害や風水害、気温の上昇等により私たちの「健康の危機」として甚大な影響を与えてしまいます。
貝原益軒
江戸時代に83年の生涯を生きる
1630年12月17日(寛永7年11月14日)~1714年10月5日(正徳4年8月27日)
筑前国(現在の福岡県)生まれ
福岡藩士 貝原寛斎の5男
幼少時代は虚弱。読書家で博識。
18歳より福岡藩に仕える。途中、藩主の怒りに触れ、7年間の浪人生活を送るも、父親の尽力の元、藩士に復帰し70歳まで勤め上げる。
1712年(82歳)に『養生訓』を発表
上記の記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目『貝原益軒』を素材として二次利用しています。(2022年10月現在)
下記は、各時代ごとの平均寿命です。
縄文時代 15 歳
弥生時代 18 歳から 28 歳
古墳時代 25 歳未満
飛鳥・奈良時代 20 歳未満
平安時代 30 歳から 40 歳
鎌倉時代 24 歳
室町時代 16 歳
安土桃山時代 34、35 歳
江戸時代 31.7 歳
明治時代 44 歳(明治 24~31 年の平均)
大正時代 43 歳(大正 10~14 年の平均)
昭和時代 ※31 歳
平成時代 83 歳
※昭和時代は、戦時中、31 歳まで下がったといわれて
います。戦後、平均寿命は延び、昭和 22 年に 50 代、昭
和 46 年に 70 代を超えるようになりました。引用元:『寿命図鑑 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑』
やまぐちかおり (イラスト) いろは出版 (編著)
江戸時代の平均寿命 31.7歳です。
貝原益軒さんは80歳を超えているので、ほぼ倍以上は生きています。
スゴイです!(>_<)
『養生訓』の中に心に残った考えがありました!
(前略) 『養生訓』第105項・第59項目より引用します。
(中略) いつも楽しんで心配をしない。これが養生の術であって、心を守る道でもある。
(中略) 心を平静にして徳を養う 心を平静にし、気を和やかにし、言葉を少なくして生をたもつことは、徳を養うとともに身体を養うことにもなる。
引用元:AXA『人生100年の歩き方』

『職場の教養』の4/7の文末に、今日の心がけ、という項目があります。
そこには、下記のように書いてありました。
今日の心がけ◆「健康に留意しましょう」
引用元:『職場の教養 2022年 4月号 10頁
4/19 人柄の良い人
4/19のテーマは「人柄の良い人」です。
素晴らしい考え方が記事となっていました!
記事の内容を本文より引用します。
Eさんの先輩に、挨拶がいつも明るく、温かさを感じる先輩がいます。
ある日、「先輩はどうしていつも、明るくいられるのですか?」と質問しました。
すると、「嫌なこともたくさんあるよ。ただ、どういう心で受けとめるかは、自分で決めることができる。
だから、できるだけ前向きに物事をとらえて、何か行動する時には、心を込めて行うようにしているよ」と言いました。
引用元:『職場の教養 2022年 4月号』22頁
この文章のどの部分に心が動かされたかというと
- 質問に対しての先輩の言葉であり
- 考え方の部分
です。
誰だって生きていれば、嬉しいコトもあれば嫌なコトもあります。
特に嫌なコトは、強烈に頭に残ってしまいます。
クローバーの場合も、フラッシュバックのように何度も頭の中に再現してしまうコトがあります。
過去のコトは、1回イヤな思いをすれば、それだけにイイのに・・・
ふとした瞬間に、思い出してしまいます(>_<)
そんな自分へのアドバイスをEさんの先輩から頂いたような気がしました。
確かに、どういう心で受けとめるかは、自分で決めることができます。
クローバーも、できるだけ前向きに物事をとらえて、行動する時は、真心を込めて行おうと思いました。
今日の心がけ◆『心を込めた挨拶から始めましょう』
引用元:『職場の教養 2022年 4月号』22頁
4/30 今に生きる
4/30のテーマは「今に生きる」です。
一休さんこと、一休宗純さんの逸話がありました。
一休さんといえば、トンチがきいて、難しい問題に直面しても楽しく解決します。
小さい頃、一休さんのアニメがテレビで放送されていて、よく見ました。
本文より引用します。
京都・大徳寺の再建に尽力した室町時代の禅師・一休宗純は、「寺がつぶれるような一大事が生じたら、この箱を開けるように」と言い遺し、夜を去りました。
長い歳月の後、寺の存続にかかわる事態が生じ、弟子たちは箱を開けました。中には「なるようになる。心配するな」と記された紙1枚があったといいます。 (中略)
明るい挨拶や整理整頓、人間関係の改善や仕事の見直しなど、先のことを心配し過ぎず、まずは目の前のことに一つひとつ丁寧に取り組んでいきましょう。
引用元:『職場の教養 2022年 4月号』33頁
この文章を読んだ時、『あの有名な一休さんも弟子たちを大切に思っていたのだな~』と感じました。
「一大事が生じたら、この箱を開けるように」というコトで、いよいよピンチの時に箱を開けますが、クローバーも何が入っているのかすごく気になりました。
そうしたら、一枚の紙があり、その中には、「なるようになる。心配するな」とのコト。
確かにそうだけど、クローバーが一休さんの弟子だったら、ふにゃふにゃと腰が抜けて、座り込んでしまったと思います。
やはり、一休さんはトンチがきいています。
その後の説明文によって、腑に落ちました。
まずは、目の前のコトに心を傾けて、目の前の課題に専念するコトが大事なんだと思った次第です。
一休宗純
一休さんも長生きしていました。
先ほど紹介した貝原益軒さん(83歳)より長生きしていました!
室町時代に生まれ、育ったにもかかわらず、87歳まで生きています。
なんと、室町時代の平均寿命は16歳です!
平均寿命の5倍です!!
室町時代 16 歳
平成時代 83 歳引用元:『寿命図鑑 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑』
やまぐちかおり (イラスト) いろは出版 (編著)
室町時代に87歳は凄すぎます!
1394年2月1日(明徳5年1月1日)~1481年12月12日(文明13年11月21日)
出生地・・・京都
後小松天皇の落胤
※落胤・・・父親に認知されない庶子、私生児。落としだね。落とし子
6歳で京都の安国寺に入門
仏教の菩薩戒禁じられた飲食、肉食、女犯を行い、妻子がいた
能筆で知られる
※能筆・・・書家の異称。世における高度な技術と教養を持った専門家。
戒律や形式にとらわれない人間臭い生き方は民衆の共感を呼んだ。
江戸時代には、彼をモデルとした『一休咄』に代表される頓智咄を生み出す元となった。
87歳(享年88歳)
上記の記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目『一休宗純』を素材として二次利用しています。(2022年10月現在)
今日の心がけ◆『今できることを探して取り組んでみましょう』
引用元:『職場の教養 2022年 4月号』33頁
まとめ
『職場の教養』2022年4月号からの心に残った3つの記事を紹介しました。
<日にち><テーマ><今日の心がけ>
- 4/7 世界保健デー 健康に留意しましょう
- 4/19 人柄の良い人 心を込めた挨拶から始めましょう
- 4/30 今に生きる 今できることを探して取り組んでみましょう
いかがでしたか?
他にも心に残る記事があったのですが、今回は最も心に残った上位3つに厳選させていただきました。
『職場の教養』は、倫理法人会に所属しているお店にて無料で頂けます。
機会がありましたら、どうぞ手に取ってみてくださいませ♪(*^▽^*)
今回の内容を読むコトで少しでもお役に
立てていただけたら『しあわせ』です♪
最後まで読んでいただき
ありがとうございま~す!(*^▽^*)
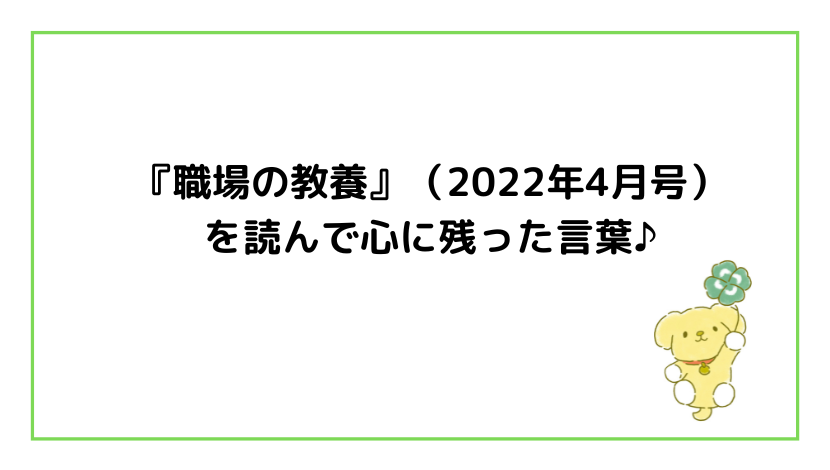




コメント